山田 敦郎
代表取締役会長
1987年
グラムコ設立
2022年
代表取締役会長に就任
前編では、新刊『パーパスブランディング ― 鼓動した9つの物語』の著者のお二人に、パーパスの潮流から日本国内での現状、良いパーパスの判断基準として機能する言葉になっていることの重要性について語っていただきました。後編では、パーパスを掲げることで得られるメリットやグローバルなビジネスにおける重要性、さらには弊社のサポート内容についてお話しいただきます。
第11回

前編はこちら
―― パーパスを掲げることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
矢野: リーダーの視点から見れば、機能するパーパスを掲げることで組織内外のステークホルダーからの共感を得て、求心力を高めることができます。その意味で、パーパスはリーダーにとって強力な経営ツールになりうるのです。
昨年から、ブリオベッカ浦安・市川というサッカーのクラブチームの理念体系を再構築するご支援をしています。ブリオベッカのトップチームは社会人リーグの頂点であるJFLで戦っているわけですが、もとは小さなサッカー教室からはじまった、地域密着型のクラブです。彼らの夢は専用のスタジアムを作り、Jリーグに昇格することです。しかし実現にはいくつもの困難な壁があります。特に大切なのはサポーター、アカデミーの選手や保護者、行政、そしてスポンサー企業といった多くのステークホルダーに関わってもらい、持続的に成長していくことです。とりわけ事業規模を大きくしていくためにはスポンサー企業からの継続的な支援が不可欠です。こうした中で、将来を見据えてパーパスを作ることになりました。
新しくできたブリオベッカのパーパスは「サッカーでともに成長し、まちを楽しくする。」です。ブリオベッカの特長は、子供たちの育成に力を入れていることです。サッカーを通して、礼儀正しく、自分の頭で考え、チャレンジし続ける姿勢を養っています。これを知った地域の企業の経営者の方々は、「ブリオベッカは、学校教育だけでは難しい人間教育に取り組んでいるクラブだ。この子たちがやがて立派な大人に育って、地域社会に貢献し、そのうちの何人かがうちの会社に入ってくれたら嬉しいな」と考え、スポンサーになってくださっているのです。通常、スポンサーの支援はトップチームの成績に左右されることが多いのですが、パーパスに共感してくださっている限り、長い目で支援していただくことができます。もちろん、トップチームの選手や、監督、コーチ陣、職員の皆さんも、ブリオベッカでの活動を通じて、それぞれの目標に向かって成長しています。Jリーグを目指す地域のクラブだからこそ掲げられる、唯一無二のパーパスになりました。

山田: これは本当に機能するタイプのパーパスですね。
矢野: また価値観や行動指針を示すバリューズも作りました。その一つには「仲間を大切にしよう。」というものがあります。例えば育成チームの中で子供のいじめがあったとすると、「それは駄目だ」とすぐに指導できるわけです。
このように理念体系が機能する言葉になっていれば、リーダーが組織の求心力を高め、方向性を示す上でとても役に立つのです。書籍の中でご紹介したセイコーグループやソニーグループのトップの方々はこのことをよく理解し、パーパスをとても上手に使って発言していらっしゃると思います。
―― 前編で紹介いただいた中で、日本国内の売上高TOP100位以内の企業におけるパーパス導入率はおおよそ46%まで増加しており、その中にはJTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)が多くいるのではないかというご意見がありました。実際多くのJTCは機能するパーパスを掲げて活用することの重要性にも気づいていると思いますか。
山田: セイコーグループやソニーグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループのように、機能するパーパスを掲げることのメリットを理解して効果的に使っておられる様を拝見すると、機能するパーパスを活用することのメリットに気づかれている賢明な企業はいらっしゃると思います。しかし、実際はまだ気づいていない企業の方が多いように感じます。当社も会員企業なので、日本経済団体連合会の会合などで大手企業のトップの方などともお目に掛かる機会があるのですが、そこでお話させていただく有名企業の方々の中には、例えばMUFGの亀澤宏規社長のような自グループのパーパスについて熱心に語られる方もおられる一方、残念ながら自社の理念、イメージや若者の共感といったことにまるで関心がない方もいらっしゃいます。
長い歴史を紡ぐ老舗企業であっても、同じシンボルマークを共有する非常に大きな企業グループであっても、パーパスという組織を鼓動させる言葉を掲げ、大いに活用することで、ご自身の代でより良く変えようと奮起していただきたいと思っています。例えば銀行業界で言えば、地方銀行は今本当に大変な時代に入っていますが、フィナンシャルホールディングス体制への移行が急速に進む中、銀行業の枠に納まることなく新しい事業に取り組んでいかねばならないという側面があります。パーパスを軸に据えてとてもうまく取り組んでおられる地銀もありますし、まだ目覚めておられないところがあるのも事実です。一歩踏み出さなくては生き残れない、金融の世界の中で取り残されてしまうという瀬戸際に来ているんですね。こうしたことを克服していく方法の一つとしても、パーパスブランディングという選択肢があるのだと思います。
矢野: 世界に取り残されるという意味では、日本の労働生産性という視点から見ても同様だと思います。世界の中でも日本の労働生産性は低く、実際に公益財団法人日本生産性本部が発表した「労働生産性の国際比較2024」によれば、2023年における日本の時間あたり労働生産性はOECD加盟国38カ国中29位、一人当たり労働生産性は38カ国中32位と、下位に位置しています。
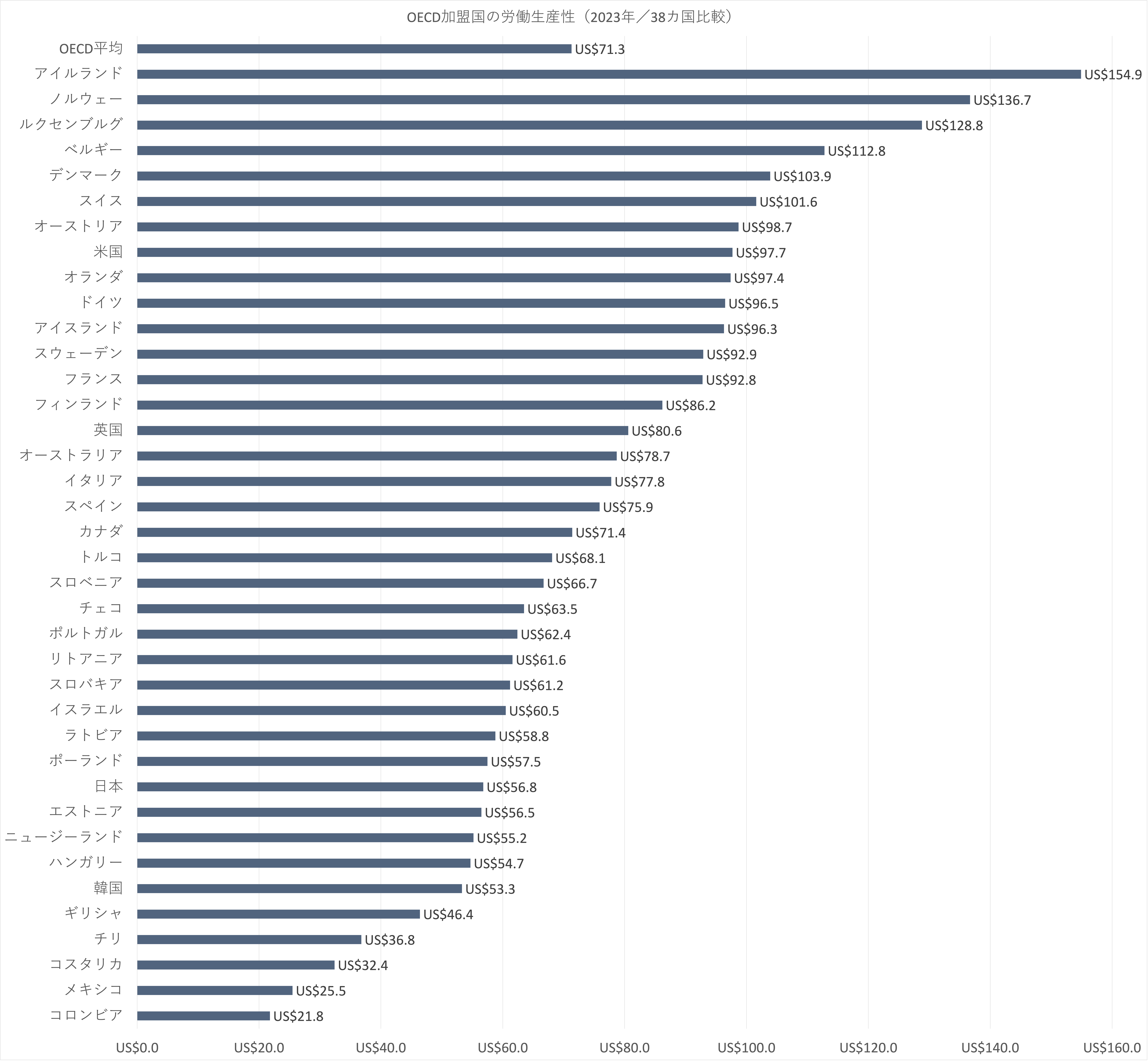
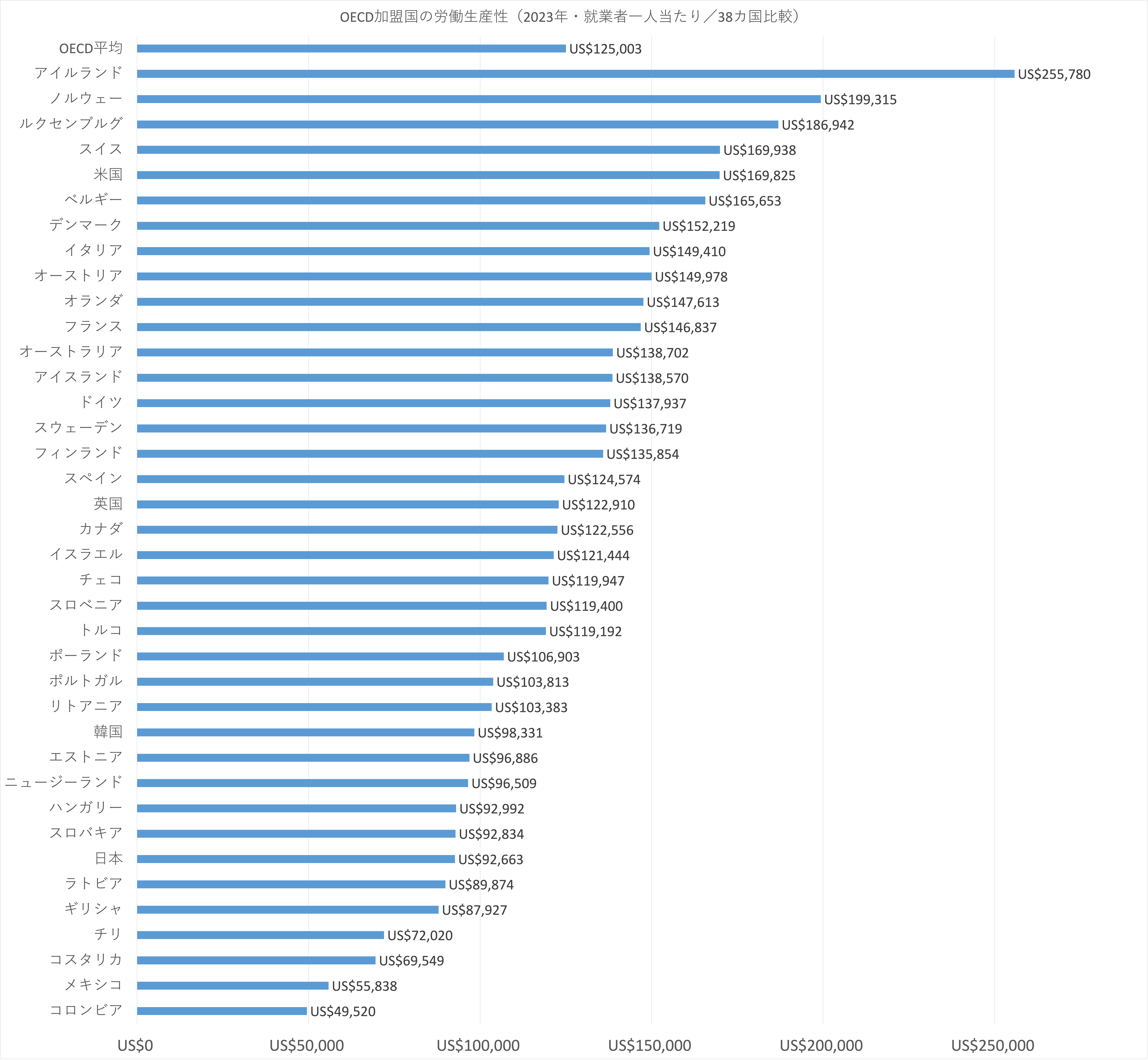
山田: 非常に低いですよね。また日本は人口減少も非常に深刻な局面に来ているわけですが、あれこれ手を打っても急に人口は増加しません。人手が足りないなんて話は、あらゆる業界で出ているわけですが、それに加えて労働生産性も低いとなると、いよいよどうしようもなくなってしまいます。さらに言えば、従業員のエンゲージメントも非常に低いという調査もあります。
矢野: 2024年に少し改善して6%になりましたが、先進国の中では最低レベルですし、全世界で見ても非常に低い数値です。言い換えると、日本で働いている人々の94%は組織に対する帰属意識を感じておらず、自分の仕事にやりがいを感じていない、ということになります。これは日本という国にとって大変な損失だと思いますし、そのような職場環境を作り出してしまっている経営者の怠慢だとも言えます。
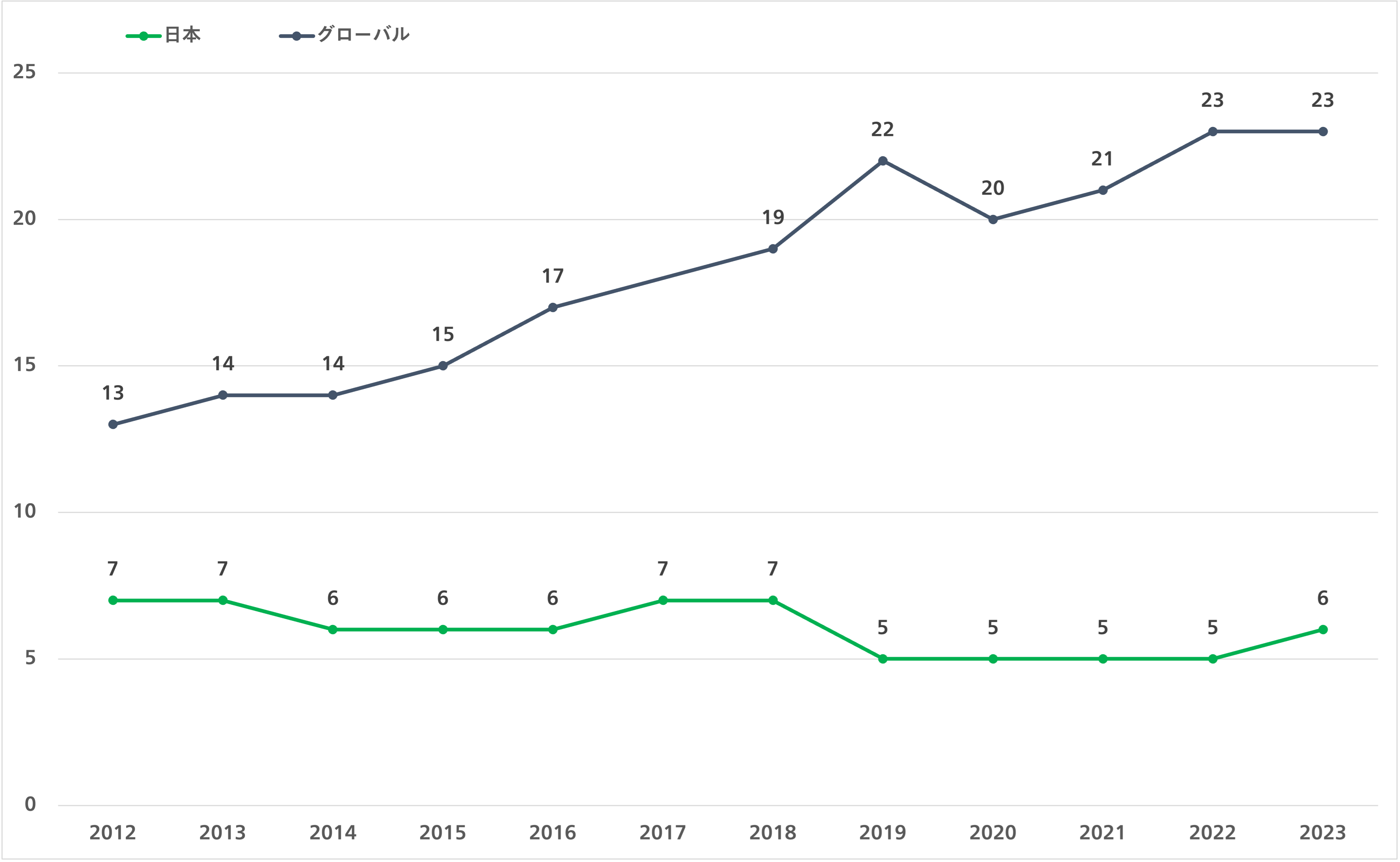
山田: パーパスを構築する際は、社員みんなで考える取り組みになるので、エンゲージメントを向上させていくという点でも、機能するパーパスを掲げ活用していくことは、非常に重要だと考えています。経営者の方々も、自身の立ち位置や、世界における自社のポジションを見ながら、ぜひ取り組んでいただきたいですね。
―― ありがとうございます。実際パーパスの実践に苦労されている企業はとても多いのではないかという感覚があります。一方でパーパスは存在意義なので、経営の中で当たり前に実践されていくものではないか、という気もしています。先ほど掲げたパーパスの言葉が機能していないというお話もありましたが、他に何か要因があるものなのでしょうか。
矢野: パーパスを作る作業というのは、本当に大変だと思います。その大変な作業を会社全体でやり切った結果、満足してしまってその後の浸透フェーズやマネジメントにしっかりとリソースを割けていない会社が多いように感じています。パーパスを実践していくには、まずトップがそのパーパス浸透推進にコミットしていること、そして部門横断組織を作り全社的な活動に繋げていること、この二点が非常に重要で、言葉自体の機能もそうですが、何よりその後の取り組みの中でちゃんと言葉を使いこなせているかが大きいのではないかと思います。
山田: まずもってトップのリーダーシップが非常に大切なのですが、中にはトップが関与しない形でパーパスを作るケースもあります。
矢野: 役員会等で最終的な承認のみ、というパターンですね。経営者が自分事にしなければいけないと思います。でないと機能しません。
山田: その通りですね。前編では、パーパスの潮流の説明の中で、ヨーロッパでは環境問題やSDGsとパーパスの深い関係性がクローズアップされたと説明しました。サステナビリティに紐づくパーパス経営がユニリーバやロレアルから広まったこともあり、ヨーロッパ企業が掲げるパーパスは環境、人権、SDGsといった問題と一体で取り組まれているものが多い印象があります。一方で、アメリカ企業が掲げるパーパスは、社内の求心力を高めていくことを中心に考えられている傾向がある。他にもあるかも知れませんが大きくはこの二パターンに分類されるかと思います。
日本に関しては、SDGsとパーパスの両方の言葉がほぼ同時期に入ってきたからか、「SDGsのどの項目にコミットしたら良いかわからないから、ちゃんとパーパスを作ろう」という一体感が生まれて、当時はサステナビリティと一体化した形のパーパスが作られていました。我々は専門性がブランディングにあるので、一体化させずパーパスとサステナビリティは並列で考えることにしました。
矢野: そもそもSDGsはSustainable Development Goalsの略称で、国連が主導して決めた開発目標なのです。しかし国の取り組みだけでは達成できないので、民間も協力を呼びかける流れの中で、企業も取り組むことになり、今に至ります。例えば清潔な水にアクセスできない人をゼロにするとか、貧困を無くすとか、結構壮大なことを目標に定めています。やろうと思ったら本当にアフリカとかに出かけて行って本気で取り組まなければいけない話です。
しかし、そんなスケールの大きなことに取り組んでいる日本企業は、ほんの一握りしかない。大半は国内でちょっといいことやって「SDGsに貢献しました」とアピールしている。定められた目標からしたら、何のインパクトもありません。先進的な技術を持ち、様々な社会課題に取り組んでいる日本企業は多いので、もっと世界で広くインパクトのある活動ができるはずです。その意味では、パーパスを上位概念に据えて、事業活動を通じてSDGsに取り組むという形が理想だと思います。
山田: その通り。並列で考えるか、一体化させるか、どちらも正解だとは思います。しかし、せっかく社内総出で取り組んでいくべき活動に対し、力の分散が起こると良くない。なので、本気で真面目に取り組むためにも、トップのリーダーシップの元に、最終的にはパーパスをもとに1本の流れに帰結するような活動にすることが肝要だと思います。

―― 経営トップの方がコミットし、自分事として本気で取り組むことが何より肝要ということですね。そのように本気で取り組もうとされている企業は沢山いらっしゃると思いますが、グラムコはどのようにサポートしているのでしょうか。
山田: 基本的には、共通の価値観を作っていくということで、掲げたパーパスがちゃんと機能しているかを問いかけながらサポートしています。我々はブランディングファームなので、ブランディング推進の一環としてサポートしています。つまりパーパスブランディングになりますが、そのクライアントのパーパスを社内にしっかりと浸透させ、結果より広く世の中に知らしめていく流れをつくるということです。
グラムコは「人、組織、世界を鼓動させる」というパーパスを掲げていますが、まさにこのパーパスブランディングのサポートを通じて我々もパーパスを実践しているのです。ブランディングはクライアント企業の皆さんにとっては欠かせないものです。なので、パーパスを原動力にしながら、より一層ブランディングを進化させることで力を尽くしたいと考えています。

矢野: 実際パーパスを導入した後、浸透実践していくための活動をどのようにしていくべきかと言う問いかけを、色々な企業から頂いています。その中の一つの答えとして、我々が現在行なっている具体的なサポート例に、状態目標の設定があります。まず、掲げたパーパスを踏まえ、いつまでにどのような状態になっていたいのか、定性的な目標を設定します。次に、それを実現するために所定の期間中実行すべき組織内・組織外の取り組みを洗い出します。そして、洗い出した取り組みの中で、設定したターゲットや優先順位に沿って取り組みを実施しモニタリングします。このサイクルを繰り返していきます。
当たり前のPDCAを回すことなのですが、共有、共感、共創の3ステップを踏んで、パーパス実践のお手伝いを、様々なメニューを通じてやっていければと考えています。最近の提案にも全て入れるようにしていて、実際に受注しサポートもしていますが、「このようなサポートが必要だ」と結構良い反応が返ってきています。
山田: そういう意味では気づきを与えているわけですね。
矢野:そうなんです。もちろん、これまで一貫して取り組んできたアイデンティティを作るというところ、ネーミング、VI、スタイルなどは引き続き取り組んでいきます。しかしもう一歩進んで「導入した後にどう浸透、実践していくのか」まで含めてサポートしていくことで、成果を出すところまで伴走できると思います。
山田: 我々としても相当な力量が必要になってきますね。
矢野: そうですね。経営トップの方々を除けば、これまで我々のコミュニケーションカウンターは、例えば経営企画室やブランド推進室など、限られた方々でした。しかしこの浸透、実践となると、それこそ事業推進部、人事部などより幅広い部署の方とお付き合いする必要が出てきます。そのような、今までお付き合いがなかった方々に自分たちの考えを伝えて、理解・共感を得て取り組んでいかなければなりません。そのためには我々自身も変えていかなければならないことも出てきます。
山田: 付き合うカウンターの幅が広くなれば、そこに新しい競合も出てくることになりますからね。我々も日々研鑽を積んでいかなければならないということです。
―― ありがとうございます。実際にパーパス実践に関わるプロジェクトに取り組んでいく中で、パーパスを社内に浸透させていきたいが、まだ説得力のあるファクトを作れていないがどうしたら良いか、と相談を受けることがあります。このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
矢野: そうですね。日本企業の従業員は真面目な方が多いので、非常に堅く考えてしまうことが多い印象です。自分のやっていることはパーパスに沿っているのか、いないのか、厳密に考えたらこの部分は繋がらないなど、とても真面目に考えてしまう。どちらかというと心意気の問題です。それこそレンガ職人の話が例えで良く出てきますよね。自分の仕事を、レンガを積んでいると思っているのか、大聖堂を作っていると思っているのかで、モチベーションが変わるというお話です。妙に自分の仕事を矮小化して、「そうは言っても私の仕事はこのレンガ1個1個を積むだけだから」と考えちゃったらそこで終わってしまう。想像力を働かせて自分の仕事が何の役立っているのか考えられるかどうかがとても大事なのです。従業員の方々がそのように自覚できないのは、恐らくトップの方がそのような意識付けをする声かけをしていないという可能性が考えられるかと思います。

山田: 基本的に持っている技術や経験から、新しいものを発想する力が足りないだけなのだと思います。実際にパーパスをもってして、世の中に掲げて前に進んでいく時に、足りないものが無いなんてあり得ないです。ミッシングピースを見つけ出して、埋めていかなければいけない。これはさきほど出ていた状態目標でもいいのですが、これから達成していく未来志向の提供価値として掲げて約束するのがいいと思います。
―― パーパス実践のPDCAサイクルのサポートをしながら、より幅広い部署の方々と関わりつつ、ブランディングの意識とパーパスの浸透を図っているのですね。ここまでお話しいただきまして、タイトルにもあります通り、パーパスは実践することで「活かす」ものであることが良くわかりました。ここでズバリ、お二人にとってパーパスを「活かす」とは、どういうことでしょうか?
山田: その観点から言わせていただければ、私は実践の前に「実装」が必要だと思います。パーパスの実装です。どういう状態かというと、パーパスが組織に包含され組織細胞のようになり、基盤として企業活動に活かされている状態です。先ほども挙がりましたが、まずは、パーパスを導入した後の共有、共感、共創のステップを踏んで、パーパスを経営や事業の中核に据えること。次に、確かにパーパスに書かれていることを体現すべく取り組むべきです。ですがそこから新製品でも、新サービスでも、新たな会社の取り組みでも、新たな何かが実際に生まれていくこと、あるいは会社が何かしら変わっていくような流れを作ることが一番だと思います。
新たな何かが生まれるという例としては、UACJを挙げておきたいと思います。同社の100%再生アルミニウム缶に充填されて売り出されたサントリーのプレミアムモルツなどは、期間限定販売でしたが、共創の次へとつながる素晴らしいチャレンジでした。
社内活動の中で、パーパスを体現できた行いをアワードとして称賛する活動はやってらっしゃる企業も多いですし、我々もサポートの一環として行います。それは大切なことなのですが、事業が実際にどう変わったのかまで追求しているところはまだ多くないと思います。
そのような中で、まさにパーパスの実践によって大胆に変わっていく流れを作ったのが、我々がサポートした東北工業大学です。東北工業大学は、「未来のくらしのエスキースを描く。」というパーパスを導入しました。このパーパスを「活かす」ために、工学部を学科制から課程制に変えました。この課程制への変更に取り組んだ工業大学というのは、芝浦工業大学に続いて、日本で2例目です。非常に大胆で革新的だと思います。
要は、学科制だと1つの専門分野を深く学ぶことになりますが、それだと社会に出た後の現場で困ることになる。1分野の専門性だけでは駄目で、複数の視点を持って重要なところを押さえられる人材を育成するため、様々な課程を自由に選択できるようにしました。それでこそ、これからの工学は、未来のくらしのエスキースを描くために、より発展していくべきという考え方なのです。もうすでにパーパスを実装して、いくつかの実践を始めているわけです。
矢野: 東北工業大学は、パーパスを実践していく10年計画を立てているそうですね。日本の企業は、今はまだ3-5年の中期経営計画が主流だと思いますが、最近は長期計画を立てる企業も少しずつ増えてきたように思います。セイコーグループの高橋社長は「経営の時間軸を無限大に引き延ばすとパーパスになる」とおっしゃいました。パーパスがしっかりしていれば、外部環境がどんなに変わってもやることはブレないし、その時々で臨機応変に対処することができるという意味合いで仰っていたのだと思います。
結局やり続けるということで、終わりはないんです。ただ、やり続ける事業活動の中で存在意義を追求し続けること、言い換えるならパーパスに反することはやらないということが非常に大切なのです。私は、会社経営の中で重要なことは、何をやって何をやらないかを峻別することだと考えています。放っておくと社員が迷って無駄な仕事をしてしまうからです。その意味でも、パーパスは大きな役割を果たしていると思います。
―― グラムコも2024年1月1日にパーパス「人、組織、世界を鼓動させる。」を宣言し、2025年3月4日に新Visual Identityをローンチ、ウェブサイトをリニューアルしました。リブランディングされたグラムコが、今後パーパスを活かし、組織を鼓動させていくために、お二人が考えていらっしゃることがありましたら、お聞かせください。
山田:グラムコのパーパスの宣言から1年ほど経ちましたが、まだまだ道半ばです。ただし、「紺屋の白袴」と言いましょうか、ブランディングファームであるにも拘わらず、仕事はクライアントの将来を考えることなのに、これまでこれほど明確に私たちの未来の構想に繋がる基盤(パーパス)を打ち出したことは、恥ずかしながらなかったので、当社としては画期的です。その意味では、本当にここからがスタートだと考えています。グラムコがこれまで行なってきたブランドのアイデンティティ基盤構築サポートは、もちろん今後も精力的に行なっていければと思います。現在その先の相談をいただいて、パーパスを実践していくための様々なサポートも行なっています。もしアイデンティティ基盤の構築が完了して1度ビジネスのご縁が途絶えてしまったとしても、その後どのように企業が自走していったのか、見届けていかなければいけません。ご縁が続くならば、出来る限り添って伴走していきたいと考えているところです。
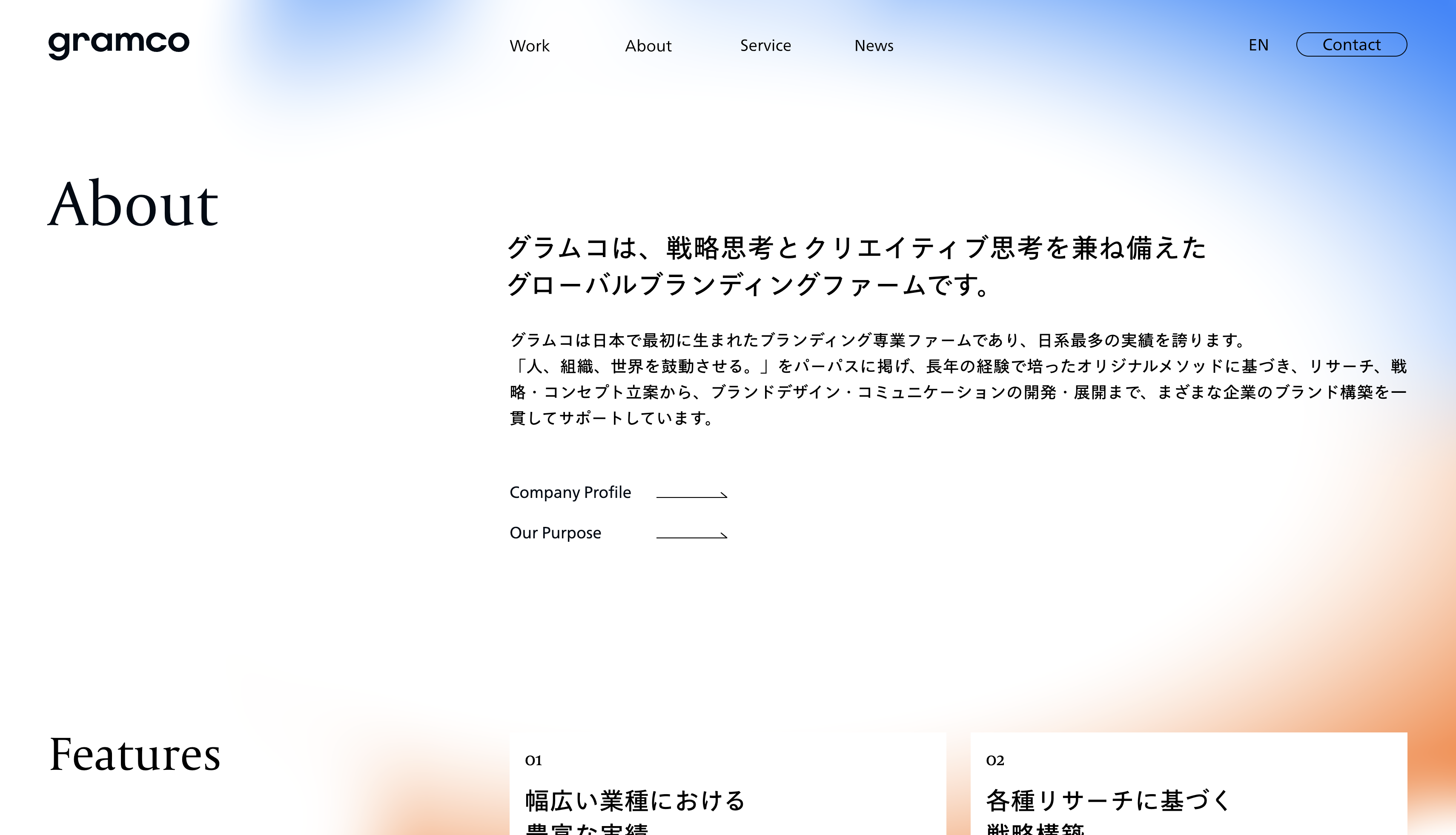

矢野: ようやくリブランディングがローンチされましたが、パーパスができてしっかり芯の通った形で作ることができたと思います。これをきっかけに、当社の従業員の皆さんの意識が変わり、連動して「グラムコ変わったね」「新しくなったね」と、外からの見る目も変わっていくといいなと考えています。何より、今回のリブランディングを通じて、色々なことでクライアントの皆さんに「我々はこうやっています」とお手本として示せるよう、しっかりとパーパスの実践を行なっていきたいと考えています。
―― ありがとうございます。最後に、パーパスの実践にお悩みの企業の皆様に一言お願いします。
山田: パーパスは万能薬では無いので、必要がなければ取り組まなくても問題ないと思います。ただし、会社を真の社会の公器にしたい、なりたいということであれば、真剣にパーパスを考え、その実践に取り組んでいただきたいと思います。周りのステークホルダーが潤うだけでなく、日本という国の未来が明るくなるよう、組織内にパーパスを実装し、グローバル規模で実践しいただければと思います。その取り組みの中でお困り事が出てきましたら、是非グラムコにご相談ください。
矢野: パーパスは非常に強い力を会社に授けてくれます。経営者の方々はそのことをよく理解いただき、使いこなしていただければと思います。使いこなすということは、つまり自分事にして、しっかりと従業員の皆さんに浸透させ、会社全体で実践するということです。パーパスは綺麗事ではなく、ビジネスをより効率的かつ世の中のためになるよう上手く回していくためのものと理解いただくと良いと思います。従業員の皆さんは、会社のパーパスに共感できたら、そのパーパスを自分の仕事で体現できるよう、意識して取り組んでみてください。そうすれば日本のエンゲージメントは良くなっていくと思います。経営者の方々もそういうものだと覚悟して取り組んでいただくと良いと思いますし、パーパスの実践に際しお悩み事があれば、グラムコがお力になりますのでご連絡ください。

代表取締役会長
1987年
グラムコ設立
2022年
代表取締役会長に就任

代表取締役社長
2012年
顧問に就任
2022年
取締役社長に就任
2024年
代表取締役社長に就任